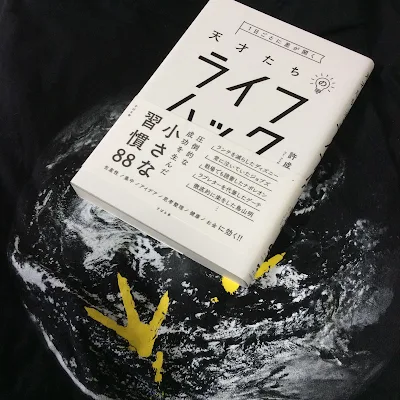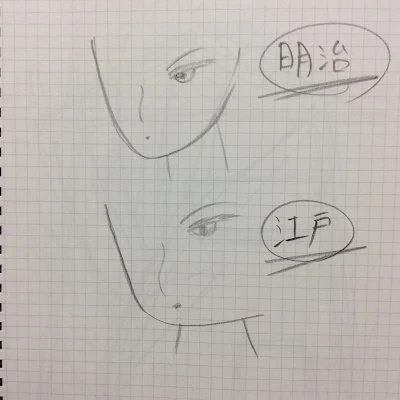刑務所の読書クラブ:教授が囚人たちと10の古典文学を読んだら
日本の翻訳は2017年で、原作は2016年。ほぼ時差がなく翻訳されてる。
場所はメリーランド州、ワシントンDCの北東20km程度のボルティモア、ジェサップ刑務所。
自分は見ていないが、刑務所 1日体験でも取り扱われた場所で、アメリカだと刑務所が民間経営の場合があり、その流れでメディア露出が多い、積極的なのだろうか?
ボルティモアと言えば、犯罪による死亡が50人/10万人で、NYは3.4人、東京は0.07人と比較して異常であるとアメリカ民主党の崩壊 2001-2020に示されてた。この場合は民主党批判が主題だが、1983年から下院で、ボルティモアが選挙区のイライジャ・カミングスが黒人貧困も犯罪件数も汚職にも無力、というか投票数を稼ぐ名目のために放置してる実態など書かれてた。
本書に戻ると、人間というものが、どれだけ環境に適応可能であり、運命論的に環境によって決まるか。正直なところ、彼らが読んだ本はどうでもいいし、彼らの発言内容もどうでもいい。読書と思考が一定の知性と行動を刺激し実現するのは自明で、本書でも事実そうだったが、終身刑を含む28歳から67歳の受刑者のうち、保護観察などで出られた人達は読書をやめ、iPhone,fcebook,ポルノ,カジノ,ストリップ、そこまで極端なものでなくとも、味が濃くて高カロリー食品を求めるなど、思想や実現などと程遠い消費者の一部となった。
読書がYoutubeに勝るという話ではない。少なくとも著者は好みとして両者に格差を暗に示してるし、自分もそれには同意する。実際に自分は、ここ数年で映画,漫画,ゲーム,ネットを合わせた時間よりも本を読むほうが楽だし利益があると判断して継続してる。ただし、それは充分にこれら娯楽を経験したからこそ言える事で、10年単位で刑務所にいた人間が、ネットや映像や性欲の刺激を求めるのは当然だとも思う。
本書でも、一般人に馴染めたからこそ、そういった傾向の消費に混ざれたのだと認めている。理想としては、そうであって欲しく無かった事も認めつつ。
受刑者の有無とは別に、結局のところ社会がそういった消費を求めてる。月に1冊の本を読んで考えるよりも、翌日には覚えていない動画を1日に10本も見て広告料と過剰な消費を促してる。
自分はもうそれにうんざりして、可能な限りそういった連中に1円も出さずに避けていられるが、それでもインターネット自体が不可欠であるのも変わらない。この辺は、特定のメディア/媒体批判というよりも、テクノロジーは貧困を救わない問題なのだろう。有無と是非は異なり2*2の4パターンを把握した上で有効を選択するのが知能であると。
本書でも言われるが、10代の頃から殺人で収容された犯罪者だろうが、本を読んで理解あるいは予想し話せる能力はある。少なくとも状況次第では、殺人犯もそれを実行する。つまり、犯罪は知能や個性によるものではない。
9月に香川県で26歳の母親が6歳と3歳の娘を車に放置して飲み歩いてた結果、2人を死亡させたとして逮捕された事件があった。子供が死んだからには逮捕は当然だが、逮捕の前に、2人の子供がいる単身母の彼女に、社会や国、あるいは親として間違ってるなどと批判する類の発言者は何かしたのだろうか? 事件が報道されても、記事には似た境遇の救済措置や、事件の経過などは全く続かない。事後の罰は必要だが、事前の策が無い、行動もしない無能が犯罪を増長、触発や量産するという自覚が無い。
教育は何を評価してきたのかや官僚の反逆などは、これらの経路依存や無能や怠慢を、ある程度の日本固有の問題として語っているが、歴史上は武力衝突が減ったとはいえ、安く買い高く売る、自身の過大評価と他者の過小評価の殺し合いは無くならず、根本的に人類が抱えた欠陥は1万年程度の結果を踏まえても改善が見られない。